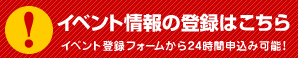生物多様性の展示、捕食関係を通して生き物のつながりを明らかに!
恐ろしい顔をしたサメばかりが展示されているかと思いきや、さにあらず。「海のハンター展 〜恵み豊かな地球の未来〜」では、魚類、哺乳類、鳥類、爬虫類など、海で生きるさまざまな生物の標本を162点も展示し、それらの生物のつながりを「食う」「食われる」を通して明らかにしています。
さまざまな生物が「食う」ためにどのように進化し、どんな能力を備えたのか。そもそも最初の魚類には口はあっても歯も顎もありませんでした。しかし歯ができ、顎を動かせるよう進化することで、より力強く獲物を捉えることができるようになったのです。

古生代最大の魚類「ダンクルオステウス」の頭骨。強力な顎を持った古生代の代表的なハンター。大きな顎で魚を捕えて食べていたが歯はない
一方、「食われる」方はどんな身を守る術を持っているのか。たとえば海の生き物の多くは食べ物を丸呑みにするため、捕食者の口よりも大きくなれば食べられることはありません。フグのように体を膨らませる術を身に付けたり、マンボウは体を大きくすることで身を守っています(ただしサメなど、歯で食いちぎる食べ方をする生き物には通用しません)。
同展では、海に生きるさまざまな生物の驚くべき捕食に関する能力を目の当たりにするとともに、多彩な生物が生息する海の素晴らしさ、そして生物のつながりをわかりやすく一望できる展覧会です。
また現在、人間は地球上で一番強いハンターです。強いからこそ、生態系を健全な状態で維持できるように守っていかなければなりません。生き物に興味を持つことで、同展の副題にもなっている「恵み豊かな地球の未来」を実現する、そんな願いも込められています。

こちらの写真、決定的瞬間のまま化石となっているのですが、どんな化石かわかりますか?

わかりやすく想像図にすると、こんな感じ。クラドキクルスに腹を食い破られたカラモプレウルス。大型魚類同士がお互いを食い合う姿の化石。よく見ると口からは尻尾が、お腹から頭が出ています

脊椎動物は顎を持つことで、より大きな獲物を食べることができるようになり、巨大化していきました。全長20mにもなったと言われる最大級の魚類「ショニサウルス」の頭骨や12mの首長竜「タラメソドン」骨格標本、そして12.5mの巨大なサメ「カルカロドン・メガロドン」

「恐竜展」などでお馴染み、国立科学博物館の真鍋真先生。古生代、中生代の生物の顎や歯の進化について説明してくれました

千数百万年前に生息していた巨大なサメ「メガロドン」の顎復元模型を前に、「海で生きる脊椎動物の捕食関係を通して生き物のつながりを明らかにすることで、多彩な生物が生息する海の素晴らしさ、そして生物の命をつなぐ営みについて理解を深めてほしい」と、同展の監修を務めた国立科学博物館の篠原現人先生

同展最大の見どころ、日本初公開となる全長3.2m、320kgの「ホホジロザメ」の全身液浸標本。2014年8月末に沖縄県本部町近海で漁の延縄にかかって死んでいたものを研究用の標本として作製したもの

内臓や筋肉など生物の形をしっかりと保存し、間近で本物の巨体を観察できる。標本の制作過程も映像で見ることができる

全長約6mの「ホホジロザメ」の顎。歯の鋭さや次から次へと歯が生えてくる様子がわかる

威圧感ナンバーワンの「シロワニ」をはじめ、金槌のような頭部が特徴的な「シロシュモクザメ」など、さまざまなサメを展示

サメ界のスピード王「アオザメ」など、まるで襲ってくるかのような迫力の展示。通常より高い位置に展示することで迫力を出し、また歯の様子がわかるようにしている

会場内のさまざまなところにサメについての詳しい解説「サメラボ」のパネルを設置。子どもでもわかりやすく説明しています

ハンティングする際のポイントもわかりやすく紹介。生物が何を手がかりに獲物を探しているかなどを紹介。海の生物の生態がわかるめずらしい映像などもたくさん

会場内では頭上にも注目! シャチやイッカクなどの骨格を展示しています

会場内は「深海」「極域」「外洋」「浅海」と、それぞれの生物を生息域でわけて展示。たくましく生きるさまざまな海の生き物を紹介し、多様な生物が生息している海の豊かさを紹介
記事が役に立ったという方はご支援くださいますと幸いです。上のボタンからOFUSE経由で寄付が可能です。コンテンツ充実のために活用させていただきます。